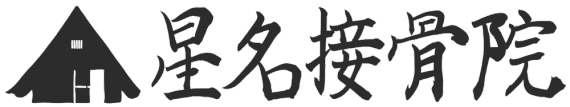photo by rpavich
石器時代のヒトは、毎日3食なんて食べていませんでした。
農耕ではなく、狩猟採集生活ですから、食物を得られるかどうかは運も関わっています。数日間食べられないこともあったでしょう。
そんな生活に適応するため、エネルギー源を蓄える機能を身についているのです。
食物をたくさん得られたときに、余分なエネルギー源を脂肪として蓄え、
食物を得られないときは、蓄えておいた脂肪を分解してエネルギー源にする、という機能です。
これを前提に、ダイエットをするにあたって考えたほうがいいことについて説明していきます。
それは、血糖値とインスリン、食欲についてです。
◆血糖値は、血液中の糖の値です
糖は、身体を動かしたり、脳が考えたりする時に必要なエネルギー源です。
少なければエネルギー不足になりますし、多すぎても身体を壊してしまいます。
そのため身体は、「多くなったら少なくなるように」「少なくなったら多くなるように」、血糖値が一定の範囲に収まるように調節しているのです。
◆インスリンは、血糖値を下げるホルモンです
血糖値が上がると、インスリンというホルモンが分泌されます。
インスリンは、血液中の糖を細胞に取り込む働きを促し、脂肪が燃焼するのを抑えます。
つまり、インスリンが働いていると、太りやすくなり、痩せにくくなるのです。
インスリンの分泌を阻害させたマウスは、いくら食べさせても太りませんし、
インスリンの分泌を促進させさマウスは、食事の量を減らしても、運動させても太るという研究報告もあります。
◆血糖値が下がると、食欲が出ます
胃の中に何かがあったとしても、血糖値が下がると食欲が出るのです。
そして、血糖値が上がると、食欲が収まります。
なかなかダイエットできない人の、血糖値とインスリン、食欲の関係は、下記のような感じです。
まず、血糖値が下がって食欲が出ます。
そして多くの場合、食事の時間、糖質を一気に摂取し、血糖値が急上昇します。
血糖値が急上昇すると、インスリンが大量に分泌されて、血液中の糖(エネルギー源)を細胞に蓄えます。
(余分なエネルギーは糖質であれ、タンパク質であれ、脂質であれ、脂肪として蓄えられます)
「血糖値の急上昇による、インスリンの大量分泌」それによって生じるのは、血糖値の急降下です。
その血糖値の低下により、また糖質が欲しくなる(食欲が出る)のです。
そして、間食にお菓子を食べ、またまた血糖値は急上昇してインスリンが分泌され、また血糖値が急降下してお腹が空くから、ご飯をいっぱい食べてしまう…(繰り返し)
痩せられない人にも色んなタイプがあり、一概には言えませんが、多くの場合はこんな感じなのだそうです。
なので次回は、ではどうすればそのスパイラルから抜け出せるのか?という話をしていきます。
(もったいぶるのもアレですので)簡単に言いますと、
「野菜から食べる」「ゆっくり食べる」「食べる前に運動をする」です。
どんなことでも、成功させるための第一歩は、まずしっかりとした知識を得ることなのだそうです。
斬新なものなんて一つもないですが、再確認していただければと思い、それらについて少しずつ説明していきます。
※ダイエットに関しては、「脂質を抑えた方がいい」「糖質を抑えた方がいい」「インスリン分泌を抑えた方がいい」「どれも関係なくてカロリーを抑えた方がいい」などなど、相互で矛盾の生じる理論やデータが数多くあります。
僕が書いている理論も、それを否定するデータもあります。
結局のところ、個人差が大きすぎて決定的な方法は無いといっても過言ではありません。一例として参考にしていただければと思います。
→次の記事『ダイエット方法論〜野菜から、ゆっくり食べる編〜』へ
→ブログ一覧へ
→アーカイブ(主要な記事一覧)へ